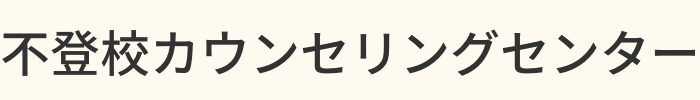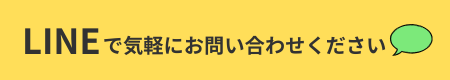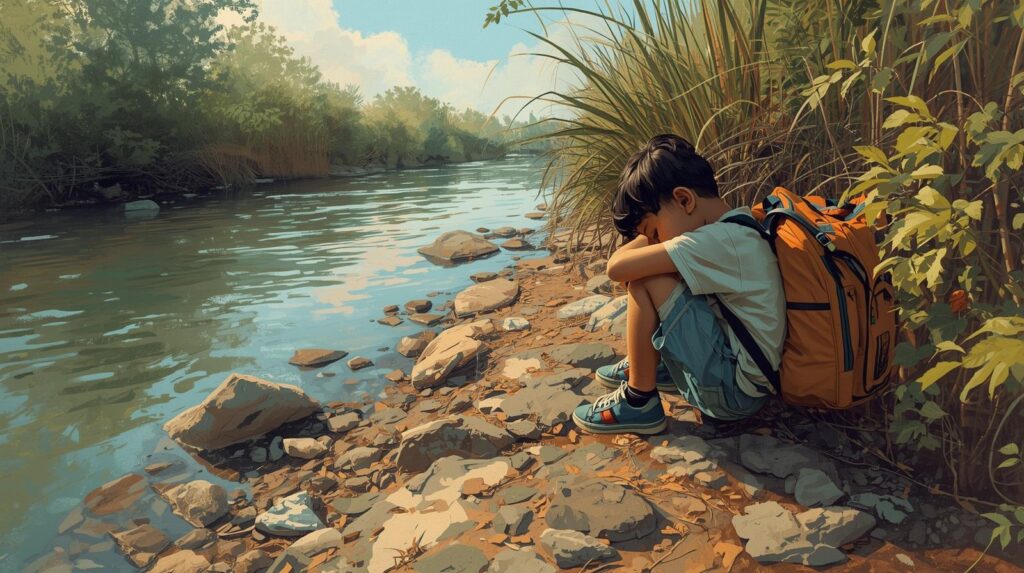
こんにちは、
不登校カウンセリングセンターの真鍋良得です。
「学校はつらくても通うもの」
そう思っている方、そう教えられてきた方は、自分が子どもの頃には、頑張って学校に通った方かもしれません。
けれど、その考えが子どもの心をすり減らしているなら、立ち止まってもいいのです。
義務教育は“心を犠牲にしてまで達成する任務”ではありません。
苦しいなら休む。
あまりにつらいなら、行かないという選択肢もあります。
「学校に行かない」というのは“逃げ”ではなく、“守る”ための行動なのです。
なぜ「休んでいい」が必要なのか
多くの親御さんは努力家です。
無理をのみ込み、場に合わせ、笑顔でがんばってきました。
その「がんばりの作法」が無意識のうちに子どもにも受け継がれ、「つらくても我慢するのが普通だよね」という空気を生みがちです。
でも、子どもは大人の縮小版ではありません。
心と体の“容量”は人それぞれ。
親が耐えられる負荷でも、子どもには重すぎることがあります。
子どもからのSOSサインに気づく
次のような変化は「限界に近いよ」の合図かもしれません。
- 朝なかなか起きられない/夜に眠れない
- 元気や表情が乏しくなる、食欲の乱れ
- 勉強や宿題に手がつかない、集中が続かない
- 人目を避ける、外出を嫌がる
- ゲームや動画に過度にのめり込む
- 学校・塾・習い事を休みがちになる
大切なのは、叱る前に「守る」こと。
まずは休息と安全の確保です。
「ほんとうの共感」は“がまんを外す”ところから
共感は「わかったふり」では育ちません。
土台にあるのは、親自身が自分のがまんに気づき、緩めること。
「私も無理して笑ってきたな」
「場に合わせるのが正解だと思ってきたな」
親自身のこの小さな自覚が、子どもへのまなざしを変えます。
ほんとうの共感は、
「あなたの気持ち、押し込めなくていいよ。」
という姿勢です。
言葉だけでなく、親の呼吸・表情・行動が同じメッセージを伝えると、子どもの緊張はほどけていきます。
今日からできる3ステップ
① 安全宣言をする
短く、はっきり伝えます。
- 「つらい日は休んでいい」
- 「行かない選択も一緒に考えよう」
- 「君の味方でいるよ」
② 感情→事実→希望 の順で聴く
- 感情:「怖かったね」「お腹がぎゅっとするんだね」
- 事実:「教室がざわざわでしんどいんだね」
- 希望:「今日はどう過ごせたら楽かな?」
“アドバイスより受け止め”を意識します。
③ 休む日のルールを“軽く”決める
- まずは睡眠と食事、日光を浴びる
- 1日の中に「安心タイム」(一緒に散歩、好きな音楽など)
- 学校対応は親が担う(欠席連絡や配慮相談は親の仕事)
よくある不安への答え
Q. 休ませたらずっと行かなくなるのでは?
A. 体と心の“過負荷”が下がると、自然な回復力が戻ります。
安心が先、前進はあと。焦りは禁物です。
Q. わがままを助長しませんか?
A. “要求を何でも通す”ことと“感情を認める”ことは別です。
気持ちは肯定、行動は一緒に調整。
例:「怖い気持ちは大事だね。今日はゆっくり休む?」
Q. 学校との関係はどうする?
A. 「今は回復を優先しています。段階的な復帰の相談をさせてください」と親が窓口になって学校とやり取りする。
別室登校・時間短縮・課題調整など、できることは意外と多いものです。
親がやめてみることリスト
- 「みんなできてるのに」「普通は」を口にする
- 元気なときの基準で今日を測る
- 先回りの説得・励まし(“がんばれ”の押し付け)
- 親自身の無理(寝不足・ワンオペを常態化)
親が自分のがまんを一段ゆるめると、家の空気が柔らかくなります。
親の安心=子どもの安全基地です。
声かけの例
- 「今日は学校より君の心を優先しよう」
- 「怖さやしんどさは、弱さじゃないよ。大事な合図だね」
- 「行かない日があっても大丈夫。自分のペースでいこう」
さいごに
学校は、幸せになるための道のひとつにすぎません。
親子が笑顔でいられるなら、遠回りに見える選択が“まっすぐな道”になることもあります。
「休んでいい」
「行かない選択もある」
その合図は、親が出せます。
今日できる小さな一歩から、親子の心を守っていきませんか。
不登校の解決法について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ、不登校カウンセリングセンターの無料メルマガをお読みください。