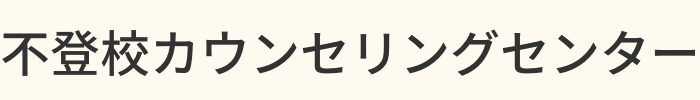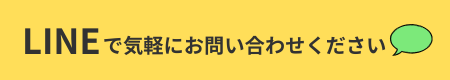「私はこのままでいい。この子もこのままでいい」から始まる、不登校の“自然な解決”
こんにちは、
不登校カウンセリングセンターの真鍋良得です。
「不登校はいつ終わるの?」——この問いは、多くの親御さんの胸に長く居座ります。
私はその問いに対し、よく、こうお伝えしています。
親であるあなたの心が安らぎ、あなた自身を「このままでいい」と認められたとき、子どもは“自分を隠さなくていい”と感じ始め、物事は自然と動き出します。
なぜ「親の安らぎ」がカギになるの?
不登校の子は、よく「自分を人前から隠す」ように振る舞います。
それは「今の自分はダメかもしれない」「見せたら否定されるかも」という怖さがあるから。
だからこそ、家が“安全基地”であることが何よりの土台になります。
そして安全基地をつくる最短ルートは、親が自分を責めるのをやめ、まず自分にOKを出すこと。
「学校に行かせられない私はダメだ」
「不登校の親だと思われるのが恥ずかしい」
——その思いをそっと下ろし、「私はこのままでいい」を自分に許すと、家の空気がやわらぎます。
その空気は子どもに伝わり、「自分を隠さなくていいかも」という感覚を育てます。
ここから、子どもの主体的な動きが少しずつ戻ってきます。
親が「自分を隠さない」ための3つのステップ
1) セルフ共感:「今の私」に〇(まる)をつける
- まず自分の感情を言葉にします。
例)「不安だ」「焦っている」「恥ずかしい」「情けない」 - さらに言葉を添えます。
例)「そう感じる私でいい」「そう思う背景がちゃんとあるよね」
ミニワーク(1日3分)
① 今日の正直な気持ちを3つ書く
② それぞれに「それでいい」と小さく〇をつける
③ 最後に深呼吸を3回
2) 罪悪感を下ろす言葉を持つ
- ×「行かせられない私はダメ」
- 〇「私は私にできるベストを尽くしている。焦らなくていい」
- ×「この子を変えなきゃ」
- 〇「この子のペースを信じて、いま必要な安心を用意しよう」
3) 小さな「好き」を一つ戻す
親が自分の好き・心地よさを少し取り戻すと、笑顔と余裕が増えます。
- 例)お気に入りの服を着る/好きな音楽を流す/10分の散歩
- 「親の“ご機嫌”は、子の“安全感”」。小さくて十分、効きます。
子どもへの関わり:結果ではなく“気持ち”を受けとめる
- ×「いつ学校行けるの?」(結果の確認)
- 〇「今日はどんな気持ち?」(今の内側に寄りそう)
- ×「頑張れば行けるでしょ?」(正論の上書き)
- 〇「行きたい気持ちも、怖い気持ちも、どっちも大事」(両方に〇)
- ×「せっかく決めたのに行かないの?」(評価)
- 〇「行こうと思えた“その気持ち”がうれしい。今日は“行かない”の気持ちに寄りそうね」(意図を尊重)
ポイントは「全肯定・全共感」。
行けても行けなくても、そのときの気持ちに〇をつける。
この積み重ねが「自分を隠さなくていい」の確信を育てます。
「親が緩む→子が動き出す」変化の流れ(見取り図)
- 親が自分を責めるのをやめる(セルフ共感・〇つけ)
- 家の空気が柔らかくなる(安心基地ができる)
- 子どもの表情・言葉が少しほぐれる(小さな会話・興味の芽)
- “自分から”の小さな行動が増える(外に出る/好きな活動に挑戦 など)
- 学校・学びへの接続が子ども主体で起こる(頻度や形は人それぞれ)
※大事なのは、親が結果を急がないこと。芽が出る土を整える役目に徹すると、子は自分のタイミングで動きます。
よくある不安Q&A
Q. 「このままでいい」は甘やかしでは?
A. 甘やかしは“責任の放棄”。
「このままでいい」は“存在の承認”です。存在が安全だと、人は自然に行動へ向かいます。
Q. 将来が不安。今、勉強は?
A. 将来の土台は「安心感」。安心が整うほど、学びの吸収力は上がります。順番は安心→行動→学び。
Q. 親が折れそうな日は?
A. それでいい日もあります。
「今日はしんどい私を休ませる」が最優先。
休むことも“育てる行動”の一部です。
今日からできる「3つの小さな実践」
- 朝の一言:「私はこのままでいい。子どももこのままでいい」
- 夕方3分のふり返り:今日の気持ちに〇を3つ
- 1日1回の“聴くだけ”:助言なしで3分、子の話(または沈黙)に寄りそう
変化は“親の内側”から伝わっていく
あるお母さんは、自分を隠す生き方をやめ、好きや弱さに〇をつけていくうちに、子どもが主体的に外へ向かう姿を目にしました。
“行けた/行けない”に一喜一憂せず、「その気持ちが出てきたこと」を大切にする声かけへ。
その結果、塾や部活に自分の意思で近づく——そんな自然な流れが生まれました。
大事なのは、特別なテクニックよりも、親の心の姿勢。
「私もこの子も、このままでいい」。
この確かな安心が、子どもの内側に「隠れなくていい」を灯します。
そして不登校は、“戦って克服する”のではなく、“ほどけて終わっていく”ものに変わります。
最後に(大切な補足)
- もし「死にたい」など命に関わる言葉が出たときは、評価や説得より“そばにいること”を最優先にし、必要に応じて学校・地域の相談窓口や専門機関へつないでください。
親が悪いわけでも、子が弱いわけでもありません。
助けを借りることも、大切な力です。 - セルフ共感や〇(まる)つけは、続けるほど精度が上がります。
完璧でなくて大丈夫。
“できた日”を数えるつもりで、今日の一歩から始めてみてください。
あなたの安らぎが、子どもの安心になります。
そして、安心が整った先に、子ども自身の“動きたい”が芽吹く。
それが、「私はこのままでいい。この子もこのままでいい」から始まる、不登校の自然な解決です。
不登校の解決法について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ、不登校カウンセリングセンターの無料メルマガをお読みください。