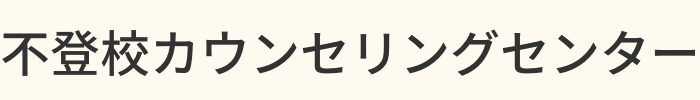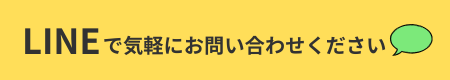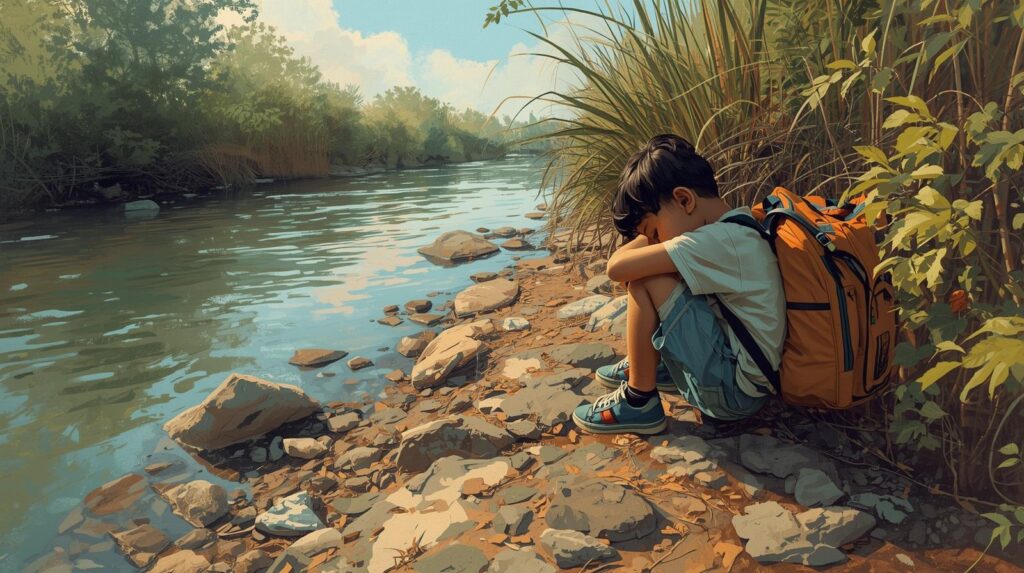
こんにちは、
不登校カウンセリングセンターの真鍋良得です。
「挨拶がきちんとできる子はいい子」
「お手伝いができる子はいい子」
「宿題をきちんとやる子はいい子」
——親としては、ごく自然に思えることですよね。
でも、この“良い子”の基準を強く求めすぎると、子どもの心を追い詰めてしまうことがあります。
「できない=ダメな子」という刷り込み
親の価値観が「できる子が良い子」「できない子はダメな子」になってしまうと、
子どもは「自分はダメなんだ」と自己否定するようになります。
例えば、朝起きられないとき。
「ちゃんと起きないとダメ」と責められると、子どもはただの疲れや不安を「怠け」と思い込みます。
また、宿題を忘れたとき。
「勉強しないとダメ」と繰り返し言われると、自分に自信を持てなくなっていきます。
不登校につながる“見えないプレッシャー”
実際に、不登校の子どもたちの多くが「自分は甘えている」「ダメな子だから嫌われる」と感じています。
その背景には、親が無意識に持っている「こうあってほしい」という期待があることが少なくありません。
子どもは親の顔色を敏感に読み取り、
「できない自分は愛されない」と思い込んでしまうのです。
その積み重ねが、劣等感や不安を強め、
やがて学校に行く力を奪ってしまうことにもなりかねません。
大切なのは“行動”ではなく“気持ち”に目を向けること
行動ばかりに目を向けるのではなく、
その裏にある気持ちを感じ取ってあげることが大切です。
- 朝起きられない → 体が疲れている、気持ちが重い
- 勉強しない → 自信がない、意味を見いだせていない
- ゲームばかりする → 現実から離れて安心したい
行動を責めるより、「どんな気持ちでそうしているのかな?」と寄り添うことで、
子どもは少しずつ安心して心を開き、自分から動き出すようになります。
まとめ
「挨拶ができる子が良い子」「お手伝いができる子が良い子」
——その考え方自体が悪いわけではありません。
ただ、そこに縛られすぎると、子どもは「できない自分はダメ」と苦しくなってしまいます。
子どもを“行動”で判断するのではなく、
“心”に寄り添うことが、不登校を解決する大きなカギになります。
不登校の解決法について、もっと詳しく知りたい方は、ぜひ、不登校カウンセリングセンターの無料メルマガをお読みください。